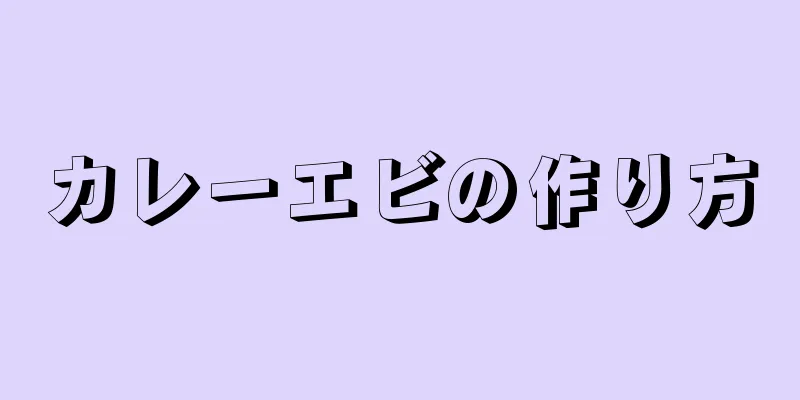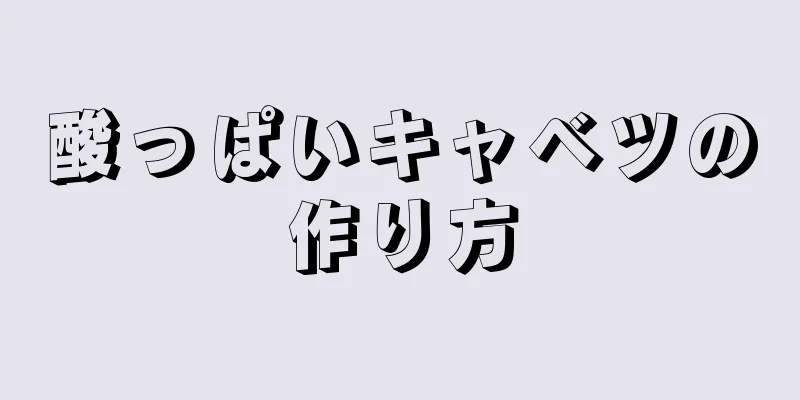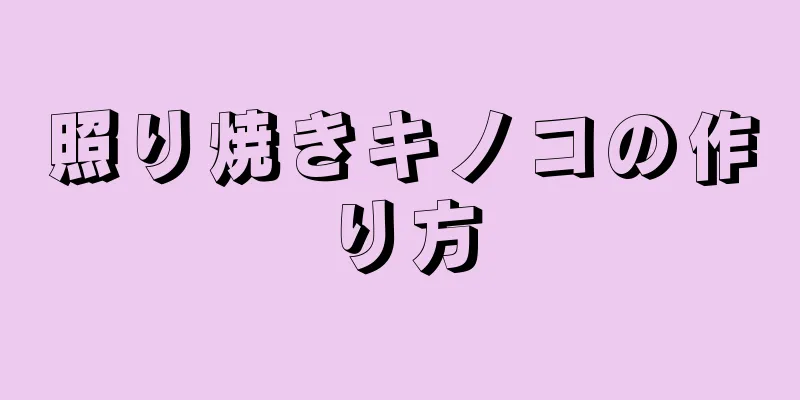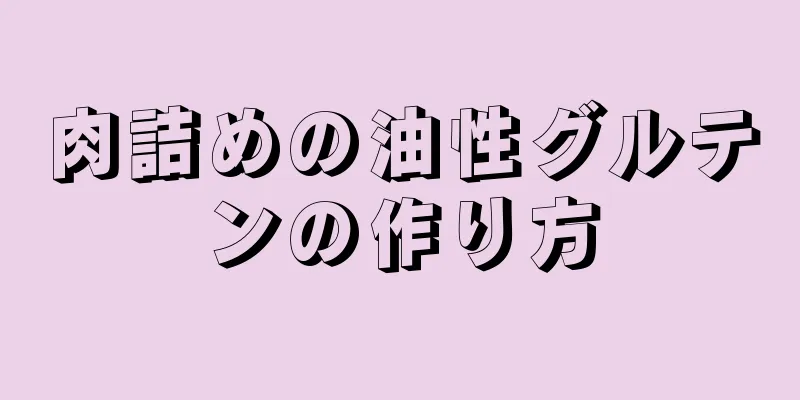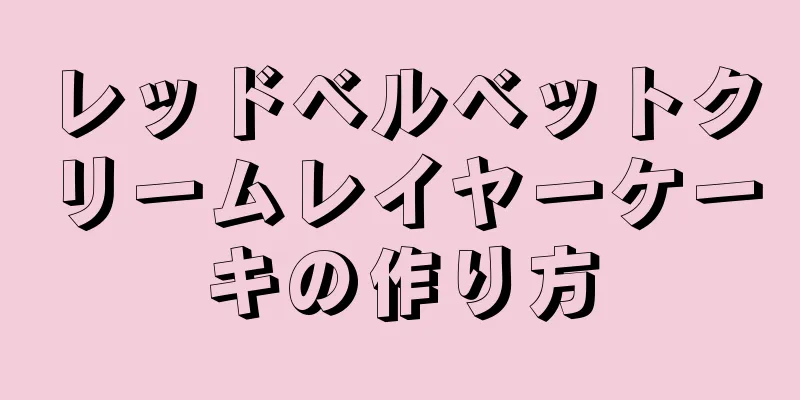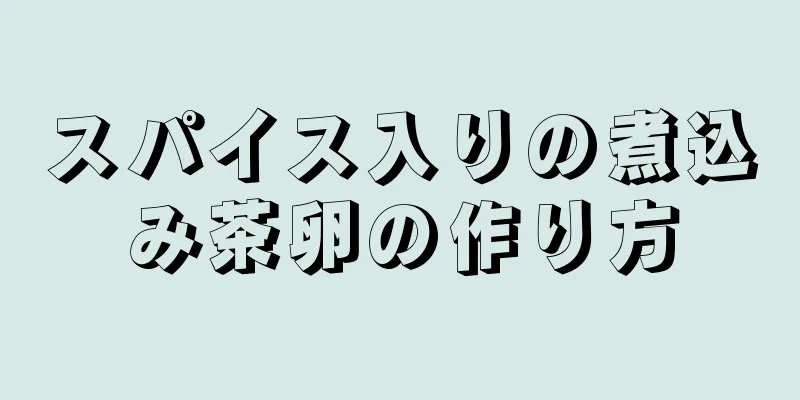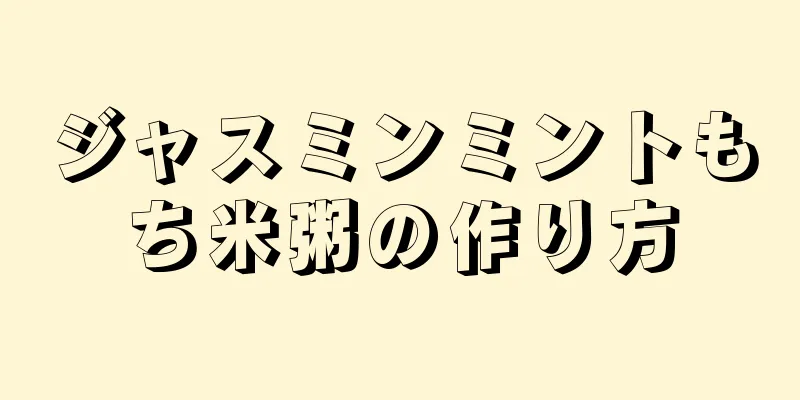カニを食べ過ぎる
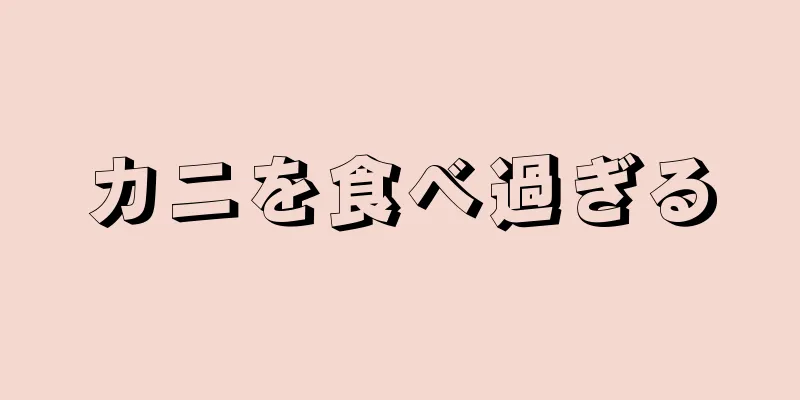
|
川ガニは冷たい食べ物なので、食べ過ぎると下痢を起こしやすいので注意が必要です。特に月経中の女性が川ガニを食べると子宮冷えや月経困難症になりやすいです。川ガニを食べ過ぎると体に害があるので、食べ過ぎはおすすめできません。川ガニを適度に摂取すればタンパク質を補給でき、味も比較的甘いので、誰でも食べられます。 カニを食べ過ぎるとどうなるのでしょうか? 1. 脾臓と胃が冷えやすい 川ガニは冷たい性質を持っています。食べ過ぎると脾臓と胃が冷え、下痢、腹部膨張、腹痛などの症状を引き起こします。月経中の女性は食べ過ぎないようにしてください。そうしないと、子宮が冷え、月経困難症、月経血の減少、さらには閉経を経験します。 2. アレルギー症状 川ガニを食べ過ぎるとアレルギー反応を起こすことがあります。軽度の場合は下痢、腹痛、嘔吐などの症状が現れることがあります。重度の場合は全身的なアレルギー症状が現れることもあります。 3. 心血管疾患や脳血管疾患にかかりやすい 川ガニを食べる場合、主成分であるカニ卵やカニペーストにはコレステロールが極めて多く含まれており、食べ過ぎると心血管系や脳血管系への負担が大きくなり、高脂血症、高血圧、脳血栓症などの心血管系や脳血管系の疾患を引き起こしやすくなります。 川ガニの食べ方 1. 蒸し蟹 蒸し川ガニは簡単に作れて、より本格的な味が楽しめます。生きたカワガニを鍋に入れ、適量のきれいな水を注ぎ、蓋をして約20分間浸します。これを数回繰り返して、カワガニをきれいにします。蒸し器にきれいな水を入れ、きれいに洗ったカワガニを腹を上にして鍋に入れ、蓋をして強火で水を沸騰させ、8分間蒸します。カワガニは長く蒸しすぎないように注意してください。 2. 川ガニの酢漬け ブラシを使ってカニの甲羅を何度も洗い、塩を入れたきれいな水を入れた洗面器にカニを入れ、しばらく置いて胃腸の汚れを吐き出させます。これを2、3回繰り返してから漬け込みます。醤油、紹興酒、ニンニク、タマネギ、花椒、唐辛子、生姜、砂糖などの漬け汁を用意し、川ガニに漬け汁を入れ、冷蔵庫で24時間保存します。その後、取り出して食べることができます。カニの殻を剥き、エラ、内臓などの部分を捨て、切り開いて唐辛子酢に浸してから食べます。 3. カニ麺 生きたカニを取り出し、きれいにし、カニの殻を剥いて両側のエラを取り除き、カニを真ん中で切り、切り口に乾いた澱粉をまぶします。火をつけて油を沸騰させ、ネギとショウガを加えて炒めます。次に川ガニを加えて炒めます。水を少し加えて沸騰させます。最後に麺を加えて5~10分ほど煮ます。適量の塩とネギのみじん切りをふりかけてお召し上がりください。 4. 寄生虫感染にかかりやすい 川ガニが持つ寄生虫や菌類は、特に生ガニの場合は高温下では完全に除去できないため、生ガニは食べないようにしてください。調理済みのカニであっても、食べ過ぎると寄生虫感染を起こす可能性があるので、適度に食べるようにしましょう。 |
推薦する
ニンニク炒めナスの作り方
多くの女の子が食べ物が美味しくないと不満を言い、ほとんど食べませんでした。栄養失調や体力低下を引き起...
紫芋とソーセージの煮込みご飯の作り方
美味しい食べ物に出会うと、IQがゼロになってしまう人が多いと思います。ダイエットをしていて、食欲を満...
自分で肉まんを作る方法
健康的な食事とバランスのとれた栄養は、私たちの体が健康でいるための重要な保証です。レストランで食事を...
朝にプルメリアを飲むのは良いことでしょうか?
多くの子供たちは、年上の人が朝にプルメリアを飲んでいるのを見て、両親に卵を使ったさまざまな食べ物を食...
トムヤムスープの作り方
外国の地ではよそ者なので、休暇中は家族が恋しくなります。建国記念日が近づいていますが、ホームシックに...
柔らかい豆腐と卵の作り方
中国にはいろいろなものがありますが、見に行ってみませんか?ほとんどの人の答えは「はい」だと思います。...
ローズかぼちゃ蒸しパンの作り方
諺にあるように、食べ物は人間にとって最も重要なものです。食べ物はすべての人の生活において重要な役割を...
卵クッキーの作り方
健康であれば、それを大切にすることを学ばなければなりません。毎日の食事に注意を払うことは健康維持の重...
桑の実のムースの作り方
毎日外食していると、正直に言うと屋台の食べ物は必ずしもきれいではなく、すぐに飽きてしまいます。実は、...
エビトーストロールの作り方
健康維持は、食事など生活の最も基本的なレベルから始めることを要求する心の状態です。さて、今回はエビト...
保温法でヨーグルトを作る方法
食べ方はいろいろありますが、健康的な食べ物を摂らなければなりません。健康になるには自分で作る必要があ...
電子レンジで豚耳の黒豆ソース煮を作る方法
料理ができる人は実はとても魅力的なので、もし男子が彼女を作りたいなら、料理ができることは間違いなく大...
クリスピーチキンバーガーの作り方
病気は静かにやってきます。そして、それは私たちがいつも無差別に外食していることが原因である可能性が高...
甘酸っぱいナスの作り方
甘酸っぱいナスの甘酸っぱい味は食欲を刺激するのに効果的ですが、甘酸っぱいナスを作るときは、砂糖の量に...
蒸しケーキの作り方(家庭料理)
食生活が健康にとって特に重要であることは誰もが知っています。健康になりたいなら、毎日の食生活にもっと...